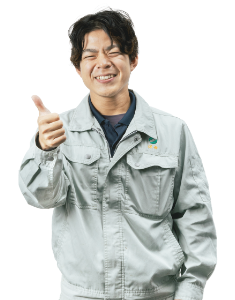DIYで使われる「SPF材(SPF木材)」の特徴は?魅力や選び方を詳しく解説

DIYで木材を使用する際、木材の扱い方が難しく困った経験はないでしょうか。そういった悩みを解決するのが「SPF材(SPF木材)」です。SPF材とは、DIY初心者でも扱いやすい木材で、ホームセンターでも一般的に販売されています。
しかし、SPF材(SPF木材)の見た目は他の木材と変わらないため、どのようなものなのか、具体的に理解している方は少ないのではないでしょうか。
この記事では、SPF材(SPF木材)の特徴やメリットなどを解説します。また、本記事の後半では、SPF材の選び方を一覧でまとめました。これからDIYにチャレンジして、本棚や小物置きなどを作ってみたい方は、ぜひ参考にしてください。
INDEX
SPF材とは成長が早く加工がしやすい3種の木材
SPF材はDIYだけでなく住宅建築など、幅広い用途で利用されている木材です。そこで、SPF材の特徴や規格を解説します。
SPF木材の特徴

SPF材は、次の3種類の木の頭文字を取って名付けられた木材のことです。
- スプルース(Spruce);トウヒ
- パイン(Pine):マツ
- ファー(Fir):モミ
これらの木は成長が早く、柔らかく加工しやすいという共通の特徴から、まとめてSPF材と呼ばれています。
SPF材は1本の木から切り出した木材のことで、3種類の樹木を混ぜた木材ではありません。
樹木の風合いなどをこだわりたい場合は、どの樹木を使ったSPF材なのかをチェックしましょう。
販売されているSPF材の規格
SPF材は、厚みと幅によって「ワンバイ材」と「ツーバイ材」の2種類の規格で販売されています。ワンバイ材は「1×○」、ツーバイ材は「2×○」と表記され、○にはカットされた幅を表す数字が入ります。
例えば「1×1」と表記されている場合は「ワンバイワン材」、「2×4」の場合は「ツーバイフォー材」と呼ぶのが一般的。
また、ワンバイ材の厚みは19mm、ツーバイ材の厚みは38mmと規格で決まっています。
少し半端ともいえる長さとなっているのは、規格として「インチ」が使われているためです。「ワンバイ材だから厚みは1cm」というわけではありませんので、サイズに注意しながら規格をチェックしましょう。
SPF材を活用する3つのメリット

SPF材が幅広い場面で使われているのは、さまざまなメリットを持ち合わせているためです。それぞれ具体的に見ていきましょう。
- 初心者でも加工できる
- 気軽に手に入る
- そのまま使える
初心者でも加工できる
タナリスCYは、無機の銅化合物と低毒性シプロコナゾールが主成分で、重金属が含まれておらず環境に優しい防腐剤です。防腐・防蟻効力が日本だけでなく海外の公的機関によって確認され、国際的に評価されている点が特徴。工場で高圧をかけて防腐剤を注入処理することで、雨水によって成分が溶け出しにくい加工を実現し、長期間の耐久性を保持します。タナリスCY加工された木材で作られたウッドデッキの耐用年数は、10年以上です。
また、釘が入りやすいため、組み立て時につまずきにくいのもメリット。木材の加工から組立まで、どの工程でも扱いやすい性質の木材ですので、DIY初心者にはSPF材が特におすすめです。
手軽に手に入る
SPF材で使われている各樹木は成長速度が早いため、他の木材よりも継続的に大量生産が可能です。無垢材でありながら比較的安く購入でき、ホームセンターなど幅広い場所で取り扱われています。
SPF材は比較的購入しやすい価格帯とされていますので、木材に多くの予算を費やせない方にも人気です。
研磨せず使用も可能
市販されているSPF材は、表面や側面が研磨された状態で販売されているケースが多いです。購入後に自分で下処理をする必要がなく、そのまま切ったり組み立てたりできますので、家具づくりの手間を大きく軽減できます。
面倒な下処理を施さなくても使えますので、必要な道具を持っていない方も安心してSP木材を使用できるでしょう。
SPF材を使う上で気をつけたいデメリット

SPF材には優れたメリットが多い一方、気をつけなければいけないデメリットもあります。
- 表面に傷が付きやすい
- シロアリなどの被害に遭いやすい
表面に傷が付きやすい
柔らかい質感のSPF材は加工しやすいですが、衝撃や傷に弱いというデメリットがあります。例えば、木材を加工するときに工具が当たってしまい、一部分だけ凹んでしまうといったケースも考えられるでしょう。
また、繊細な注意を払って無事に組み立て終わったとしても、扱い方によっては目立つ傷や凹みができてしまうかもしれません。
組み立てや加工時は傷がつかないように気を配りましょう。塗料で表面を保護するなど、傷や凹みの対策を忘れないでください。
シロアリなどの被害に遭いやすい
柔らかい質感の木材は虫に好まれやすいため、シロアリにSPF材の内部を食べられてしまい、せっかく作った家具が虫害を受けてしまうリスクもあります。
したがって、SPF材は虫の影響を受けやすい屋外での使用は可能な限り避け、質感や機能性を維持しやすい室内用の家具などに使うのがおすすめ。
もし屋外用の家具をSPF材で作りたい場合は、防虫処理や防腐加工したうえで、シロアリなどの虫からの被害を防ぎましょう。ただし、こうした加工を施すためには、専門的なDIYの工程が増えるため、ある程度作業に慣れてから屋外用家具のDIYに取り組むのがおすすめです。
SPF材の上手な選び方

SPF材は手軽に手に入る木材ですが、デリケートな質感のため、新品の木材でも品質が低下している可能性が考えられます。SPF材の選び方も確認し、希望するSPF材を購入できるようにしてください。
- 曲がり・反りの状態を確認
- ヒビや凹みをチェック
- 節のないものを選ぶ
曲がり・反りの状態を確認
SPF材は乾燥により曲がりや反りが起きやすい木材です。木材自体が曲がっていると、組み立てたときに歪みが生じたり、寸法が合わなくなったりと、見た目の悪さや機能面の低下につながります。
店頭でSPF材を購入する際には、曲がりや反りの状態を確認し、表面が平らなものを選びましょう。見た目ではわからない場合は、壁など平らな面にSPF材を合わせて曲がりや反りをチェックするのがおすすめです。
ヒビや凹みをチェック
SPF材はデリケートな性質の木材ですので、運送中や陳列時にヒビや凹みが生じるケースがあります。表面のヒビや凹みによって、釘を打つときに木材が割れてしまい、木材の買い直しが必要になるかもしれません。
また、表面にヒビや凹みがあると塗装時に色ムラが生じ、仕上がりに影響を与える可能性もあります。店頭で新品のSPF材を買う前に、必ず表面の状態を確認し、ヒビや凹みのないものを選びましょう。
節のないものを選ぶ
木材の節は樹木の雰囲気を感じる箇所の一つですので、節を気にしない方も多いでしょう。しかし、木材の節は節部分が取れる「節抜け」が起こる可能性があり、見た目の劣化や変形を引き起こす要因になるかもしれません。
SPF材を購入する際は、なるべく節の少ないものを選びましょう。また、節部分は他の部分よりも硬く加工が難しいため、節の少ない材料のほうが比較的容易に作業できます。
SPF材(SPF木材)でDIYにチャレンジ!
SPF材は柔らかい材質の木材であることから、DIY初心者でも扱いやすく綺麗な仕上がりになりやすいのが特徴です。木材の下処理が必要なく、揃える工具も少なくて済みますので、これからDIYにチャレンジしてみたい方にもSPF材がおすすめ。
mock re:(モックリー)では、SPF材を初めとする幅広い木材を用意しており、作りたいものに合わせた木材を提供しています。さらに、お客さまが作りたいものに合う木材や組み立て方の提案なども実施しています。SPF材(SPF木材)についてだけでなく、木材選びからお客さまのDIYをサポートしていますので、DIYについてお悩みの方はお気軽にmock re:へご相談ください。